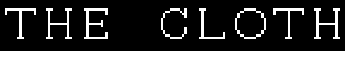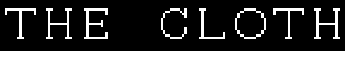平成元年6月22日 NO.8947 桐生織物協同組合広幅青年会広報宣伝委員会
6月定例役員会(6月6日)
*** 第一号議案 各委員会行事計画 ***
{技術開発委員会} 箔巻装置現在在庫13台 希望者は至急組合まで連絡下さい。
{生活改善委員会} 三青年会合同ソフトボール大会 8月27日いつもは暗く、蒸し暑い工場に閉じ込められている人、青空の下で(たぶん)思いっきり動いて、壮快な汗をかいて、気持ち良いビールを飲みましょう。試合後の懇親会会費3000円(予定)
大阪繊維機械博見学 10月上旬 我々技術屋は常に最新のハードの情報を仕入れていなければなりません。そのためにも数多くの参加を望みます。
県民の日家族慰安ディズニーランド 10月28日 彼女とのデートにも最適!
*** 第二号議案 会費納入について ***
まだ未納の人は至急組合または地区役員まで納入して下さい。その際には工場便覧とアンケート用紙も忘れずに!青年会の大事な資料です。
*** 第三号議案 その他 ***
織物組合の青年会(広幅、服地、内地)のつながりを強めるために三青年会連絡会が設立されます。
服地青年会で今秋(11月22日〜26日)海外旅行を行います。場所はジャカルタ、バリ島。費用は17〜18万円くらい。広幅青年会からの参加も歓迎しますので、希望者は組合まで連絡下さい。新婚旅行のコースとしても最高です。参加メンバーまで保証は出来ませんが・・・
*** 今月の稼動率調査(6月6日現在 サンプル数19)***
前年比稼動率 最高120% 最低80% 平均100.0%
前年比収益率 最高125% 最低80% 平均103.8%
前月比稼動率 最高120% 最低90% 平均100.9%
前月比収益率 最高120% 最低90% 平均101.8%
現在の織機稼動率 最高100% 最低90% 平均98.6% 100%稼動14件
これまで役員会で実行したアンケートの中で最も良い結果が出ました。織機稼動率はほぼ100%に接近し、前年比、前月比共に収益率は稼動率を越え、しかも100%以上となっています。これは、割と儲けの多い仕事が、平均して続いている現れです。ちなみに昨年10月の段階では前年比稼動率93.1%、同収益率90.0%、前月比稼動率81.1%、同収益率77.2%でした。日本国政府もアメリカも余り当てにならない今、今年の10月のデータは神様に祈りましょう。
消費税?どうしよう 出演 御隠居さん、クマさん
<御隠居> クマさんや、消費税、どうしたい?
<クマ> いやあ、うちじゃ売上が3000万円なんていかないし、元請けさんに聞いたらお宅じゃ必要ないだろうって言うんで請求書にも書かなかったんだけど、どうかねえ。<御隠居> そんなこと言ったってお前さんの所じゃ、せがれが今度家に入るってんで織機増やすんじゃないのかい。
<クマ> はあ、レピアを4台と工場を直さなきゃならないから5000万円の借金は辛いけど、まあ、子供のためにもう一ふんばりしなきゃ、と思っているけど・・・
<御隠居> おまえさん、それだけで150万円も黙って税金にもっていかれるんだよ。そのほかに電気だって、ガソリンだって、部品だって、機拵のSさんの請求書だってみんな3%が付いて来るのはどうする気だい?
<クマ> だって、3000万円以上売上がなかったら消費税、払わないんでしょう?
<御隠居> なに言ってんだい、さっき言ったようにもう払っているじゃないか。ここでもらわなかったらおまえさんが一方的に払い損になるんだよ。それに消費税の請求に3000万円は関係ないんだよ。それに、消費税が3%のままなんて誰が決めたんだい。竹下さんはもうやめたし、宇野さんだっていつまで持つか分からない、その次の人は「私は3%を変えません」なんて言ってないよ。欧州や米国の例でも必ず上がっているんだ、もし10%になったら、おまえさん、どうする。幸い機屋さんは今ものすごく忙しくてどこでも織機を必死に捜しているそうじゃないか、今からもらっておかないと景気が悪くなってから請求したってくれるはずが無いじゃないか。
<クマ> だって、もし請求書に3%を書いて、元請けの心証を悪くしたらどうします。
<御隠居> おまえさんも何にも考えないね。何のために協業会だの、青年会だの、あるんだい。こんな時にまとまってこそ本当の組合じゃないか。ここで動かなかったら本当に「入っていてもメリットが無い」と言われるよ。元請けだって鬼や蛇じゃ無いんだから、みんなでまとまって交渉すればきっと分かってくれるよ。
<クマ> 分かりました、御隠居さん。何とかみんなと話して、俺達も消費税もらえるように頑張ってみます。
10周年記念歴代部長、会長あいさつ
早いもので、青年会(青年部)も設立以来、10年がたちました。ここで歴代の部長、会長に昔を振り返っていただき、その足跡を確認したいと思います。
初代 木村達史 1980〜1981年
青年会発足して10周年、おめでとうございます。昭和54年、各地区協業会長のきもいりで準備委員会が設立され、翌55年発会。当初は目的すら定まらないままの発会でありましたが、定期的に集まり、同じ立場としての情報交換をしていく事に意義を認めあっての年月でありました。当時の事を回想しますと、部長選出に当たって、議論百出でまとまらず、小堀さんらの後押しと、私自身の若気の至りで私が口を切った次第だったことが懐かしく思われます。一つの例として10年前はレピア織機が幾らもなかったのに比べ、現在の状況を見ると、青年会の活動の成果が如実に表れたようで素晴らしいことであります。
これからも活動が大きくなることは良いことでしょうが、ある程度の所でセーブしないと消化不良をおこすのでは、と言うのが初代部長の一抹の不安です。
二代目 須永輝男 1982年
十年一昔とか、光陰矢のごとしと申しますが、早いもので、青年部が出来て十年、二年間は木村部長を中心に順調にきたのですが、三年目に入り、それぞれが忙しい中をやりくりしながら青年部の活動をしているので、部長のなり手がいなくて、役員を決める会議が夜中までかかってしまったのがつい昨日の様に思い出されます。青年部を潰してしまってはしょうがないと、園田さん、奥沢さん、森島さんと私が名乗りを上げ、一番年長の私がその年の部長をすることになりましたが、難産の末の役員決定だったのが幸いしたようで、その後の活動は大変うまく行ったようです。また、一年間のオブザーバーとして出席していた適正工賃審議会に、その年から委員として出席したことが印象に残っています。地場産業としての織物業がいつまでも中心に位置し、その後継者たるべき青年部の皆様の活躍を大いに期待しています。
三代目 園田善一 1983年
私の場合、須永前部長の直接指名での部長就任で、ようやく黎明期を抜けたばかりの青年部に組合内部に対する発言力増強を狙って腐心しました。そのための活動が、その年、僅差で争ったいくつかの選挙でした。当初、青年会設立の項目の一つに「政治的に中立」と言うのがあり、選挙活動はその主旨に反したのですが、青年会が単なる「賃機の集まり」と言う組合上部の認識を改めさせるためにどうしても必要と感じたからです。現在では設立当時の目標である機械の近代化、同業者同士のつながり、そして組合内部での地位の向上をある程度達成したと思うので、今後は別な目標、例えば、織物のソフト(新しいものを自分達で創りあげる)面で活躍してもらいたいと思います。そして、余りに広がりすぎた活動も整理、統合が必要でしょう。
四代目 奥沢秀年 1984年
青年部創立、まだ十年?いや、もう十年の感の方が強い私が四代目部長という重責を一年過ごせたのも、青年部活動が、「この方向でいいのかなー」という、どちらかと言うと安定期に入った頃であったためと、先代部長の作られた指導法と部員一人一人の協力があってこそ、と思われる。青年部初の海外研修(台湾)などは前園田部長の敷いたレールの上を走ったにすぎず、自分が青年部活動に何が出来たかといま思うと思い出せないほど小さかったように感じられると同時に、もっと勇気が必要であった。こういう組織は役員だけの活動になりがちだが、現在まで会員のための組織活動が活発に行われているのは役員それぞれの方の努力の成果がうかがえ、各工場間、また、親企業との情報交換、交流がスムーズに行えるようになったのは青年部活動の成果と言えるだろう。今後も役員の方々の勇断で新事業の開発と会員一人一人の活発な活動に期待したい。
五代目 新倉啓右 1985〜1986年
奥沢部長の時に副部長だった自分が、いわば順送りの形で部長になり、2年間を務めた訳だが、個人的な意見ではあるが、部長は1年よりも2年位はやった方がその人間のカラーが出てよいと思う。自分自身も、選挙があったり、いろいろと仕事に支障のきたすところが無かった訳では無いが、それまで狭かった交際範囲、対外的な広がりが著しく大きくなり、それが1年目よりも2年目が、さらなる充実となったような気がする。
任期中に行った青年部2度目の海外研修(フィリピン)は、当時、円高進行の真っ最中であり、1ドル170円くらいだった頃、すでにマニラの闇ルートでは150円であり、「日本で150円を割ったらどうしよう」と話したことが思い出される。外国に行くことは、日本では想像もできない事実に巡り会うことであり、貧富の差があれほど大きいとは、日給が400円〜500円とは、無ければ無いなりにあれほど工夫しているとは、思っても見なかった。
また、現在の地場産センター設立の時期でもあり、我々もわずかながら出資したときは個人個人がよりよく活用できるように、という訳だったのが、状況として余りはっきりしているとは思えないのは残念だ。
最後に、最近、何か行事を行おうと思っても、参加する人数が減少しているのはどうしたものだろうか。しっかりとした参加と実行の精神を失わないでもらいたい。
六代目 世取山一男 1987年
なんとなく会長になった自分だが、なんとなく話題に乗せた箔巻装置が青年会の製造販売という事態になり、結局は青年会が独自に開発し、普及させた最初の事例になってしまった。これはそれなりに記念になりそうだ。秋には小松地方の工場見学に行ったが、少人数だったため、自前のワゴンに乗り込んでの長旅で、運転手をやってもらった伊地知氏にはなんとなく迷惑をかけてしまったようだ。年度末の方には新たに結成された「イベント委員会」がなんとなくの運営で大変苦労したが、前原会長に移ってからなんとなく軌道に乗ったのがうれしい。
七代目 前原幸児 1988年
私がこの業界に入った20年前にはどこの会社にも、また、工場にも若い娘が大勢いました。それが年々年をとり、老人がほとんどという状況が多くなってしまいました。また、青年部も年々平均年齢が上がり、青年部員は若干名になってしまいました。こんな折り、先日東京の問屋に行ったとき、インテリア部の部長さんが、次のような話をしていました。
以前(昔)、品物は日本から調達していたが、それが韓国、台湾になり、タイ、マレーシアそれから最近ではインドネシア、パキスタンである。ところが、最近では日本のニーズ、価格、政情の安定、品質、センスの良さからイタリアが見直されている。
日本で繊維の生産で残るのは大変ですね、と言うと、トシヨリばかりだからね、と一笑にふされてしまった。
現在、桐生産地はショール生産で燃えているが、販売の現場ではそれほどでもなく、今一番心配しているのは設備を新しくして(ここ数年、比較的好況のせいか、設備増強が目ざましい)、その後のポスト・ショールです。早ければ今年の終盤から、と言う近未来的なこのような心配から、これから将来、どの様な品物を作って売ったら良いのか、それを考えるのが桐生産地と我々に残された課題の様な気がします。
お知らせ
広沢地区役員の中里喜一会員が6月4日(日)グリーンヒル高砂で飯塚三恵子さんと生涯の契りを結ばれました。
= = = = = = =
小野里公男さん(大間々、小野里紀善副会長の父)の葬儀が6月6日行われました